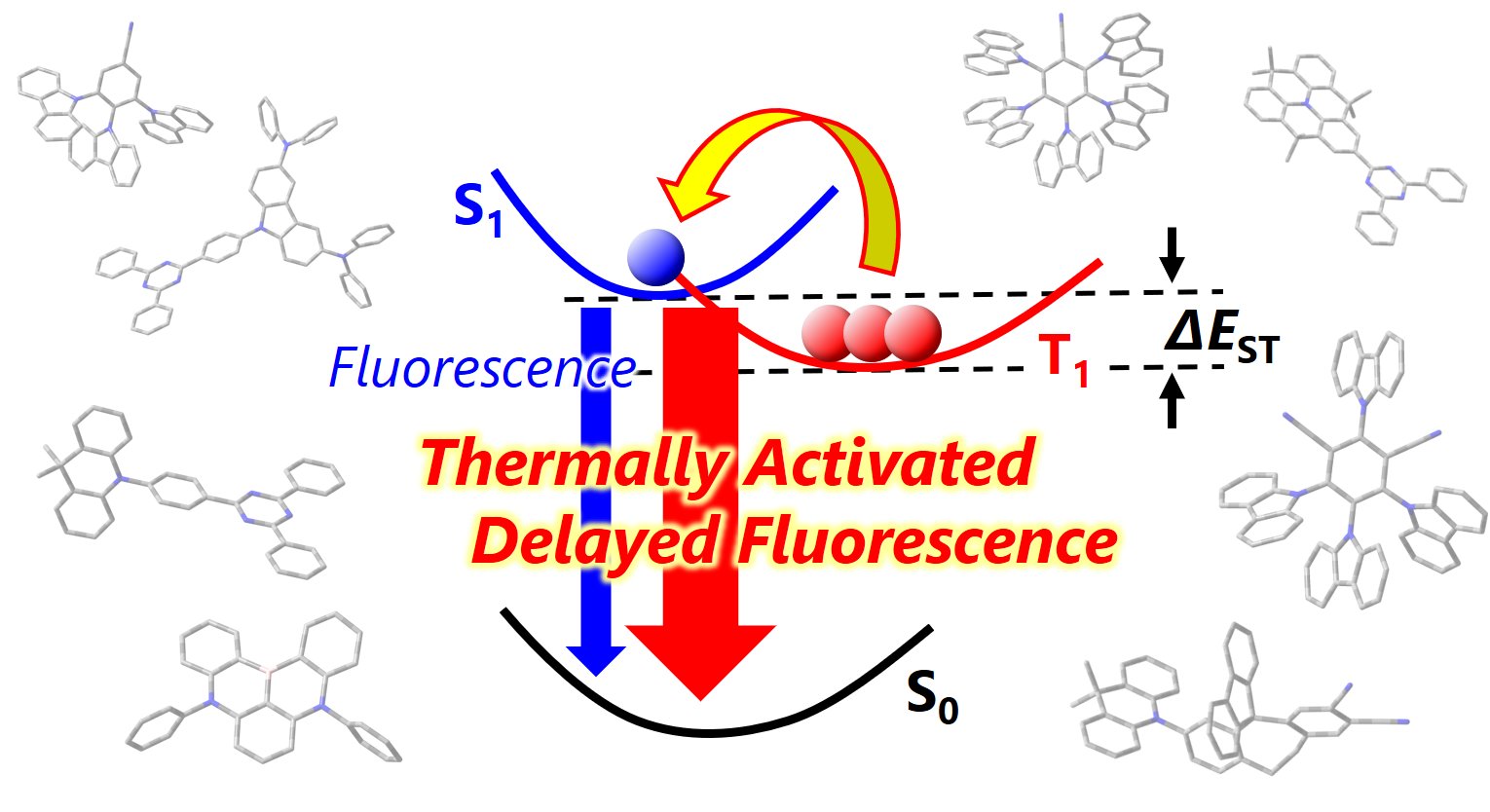第66回の海外化学者インタビューは、フランセスコ・ステラッチ教授です。マサチューセッツ工科大学(訳注:現在はスイス連邦工科大学ローザンヌ校に所属)の材料化学/工学部で超分子材料化学を研究しており、特に超分子集合体が特定のナノ構造を取るときに示す外界との相互作用に興味を持っています。それではインタビューをどうぞ。
Q. あなたが化学者になった理由は?
実のところ自分は材料科学者でして、化学者は私の「いとこ」 です。材料科学者になる選択をしたのは、物理学と化学のどちらがいいか決められなかったからで、材料科学はよい妥協点に思えたからです。キャリアが進むにつれて、ますます化学に傾くようになりましたが、それでもその選択には心から満足しています。
Q. もし化学者でなかったら、何になりたいですか?またその理由は?
そうですね、科学を選んだ理由は、それが周りの人々を助け、最終的にはあらゆる人の生活的改善につながる知識を発展させる方法だとかつて感じ、また今も感じ続けているからです。この夢は自らを日々駆り立てる、他の何にも代えがたいものです。ですから、もし科学者になれなかったら、同じ精神を持つ政治家になりたいと思ったでしょう。一方、私の昔からの夢は、アンリ・カルティエ=ブレッソンのような、芸術的なタッチで世界に語りかける写真家になることです。
Q. 概して化学者はどのように世界に貢献する事ができますか?
私たちは誰でも、自らの才能をこの世界の生活的改善に使うことができます。そのために使う資源はどんどん少なくなり、病気や痛みが人生にもたらす困難を和らげることができます。遠き未来の夢は、科学を使って、豊かな国と貧しい国の格差をなくすことです。技術が均等配分されている世界では、(たとえば水のような)天然資源への不均等アクセスに由来する格差は緩和される(…と思います)。
Q.あなたがもし歴史上の人物と夕食を共にすることができたら誰と?またその理由は?
うーん、これは難しいね。サッカー選手でもいいですか?・・・冗談ですよ。他人が彼らを必要としなかった時代に、世界を変えた方々と夕食を共にしたいと思います。彼らはものごとをより良くするために、愛をもってそうしたのです。ですから、アッシジの聖フランチェスコとガンディーはマイリストに載っています。とはいえ、たった一度の夕食(あまりに短すぎて質問をしきれませんが・・・)なら、クレオパトラなんてどうでしょうか?・・・これも冗談ですよ。.
Q. あなたが最後に研究室で実験を行ったのはいつですか?また、その内容は?
真っ当な実験でしょうか?・・・覚えていません。とてもとても悲しいことに!!!ポスドク最後の実験が何だったかさえ覚えていません。そう、恋人への別れのキスみたいなものですよね!実習の授業をしている都合、今も多くの実験をしていますが、DLSを用いて希薄溶液中の高分子コイルのサイズを測定したのが最後の実験です。真に研究指向である実験のスリルに勝るものはありません。
Q.もしあなたが砂漠の島に取り残されたら、どんな本や音楽が必要ですか?1つだけ答えてください。
まだ全部読んでおらず、ずっと読み終えたいと思っていた本にします。それはダンテ・アリギエーリの「神曲」です。
CDはピンク・フロイドのものにするでしょう。選ぶのは本当に大変ですが、どの曲も大好きです。
[amazonjs asin=”4309205496″ locale=”JP” title=”神曲【完全版】”]原文:Reactions – Francesco Stellacci
※このインタビューは2008年5月30日に公開されました。