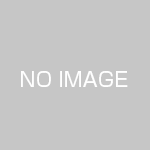紅麹問題に進展がありました。
各新聞社が下記のように報道しています。
小林製薬(大阪市)がつくる機能性表示食品の摂取者に健康被害が相次いでいる問題で、厚生労働省は29日、小林製薬のサプリメントに「プベルル酸」という物質が意図せずに含まれていたことを明らかにした。今後、小林製薬と厚労省はこの物質の毒性などを調べる。
厚労省によると、プベルル酸は青カビからつくられる天然の化合物で、どういう理由で混入したのかはまだ不明という。抗生物質としての特性があり、抗マラリア効果があるほど「毒性は非常に高い」というが、腎臓への影響は現時点ではわかっていない。
引用:朝日新聞社
厚生労働省は29日、小林製薬の紅麹(こうじ)原料を含む機能性表示食品による健康被害を巡り、同社が厚労省に対し腎疾患の原因と推定される「未知の成分」が「プベルル酸」の可能性があると報告したと発表した。
引用元:日本経済新聞
上記のように、プベルル酸が混入した物質なのではないかと浮上してきました。
プベルル酸は下記のような構造であることがわかっています。

プベルル酸は北里大学の大村、砂塚らのグループによって抗マラリア活性を持つ化合物として単離・合成されているトロポノイドの一種です。[1][2]
最初の単離は1932年。BirkinshawとRaistrickらによって、P. puberulum Bainierが産生する化合物として単離されました。[3]
トロポノイドは非ベンゼン系芳香族の1つの化合物群であり、ヒノキチオールなどが有名な化合物として知られています。
まずはプベルル酸とヒノキの香りの成分であるヒノキチオールを見比べてみましょう。

プベルル酸はヒノキの成分と基本骨格は同じでありながらも、抗マラリア活性を有することが知られています。
また、大村・砂塚らのグループによって同時にヒト細胞株MRC-5に対する細胞傷害能(肺の細胞であり正常細胞として用いられる)が調査されており、プベルル酸はそのIC50値が288.7 μMであることがわかっているとのことでした。
今回の混入物質がプベルル酸であるかどうか、またそうであった場合に原因物質がプベルル酸であったかはわかっていませんが、生理活性の部分についてはさらなる調査が求められます。
全合成報告
さて、ここまで速報としてせっかくプベルル酸に関する情報をお伝え致しましたので、抗マラリア活性を有するプベルル酸はどのようにして人工合成されたのか(not生合成)を大村グループらの合成法を紹介致します。

大村・砂塚らのプベルル酸の全合成の概略スキーム
大村・砂塚らはD-ガラクトースを出発原料として全合成しました。
酸化された5炭素のビルディングブロックとして活用し、還元的な増炭反応とその後のオレフィンメタセシスにより、炭素7員環を構築しました。
その後、Parikh–Doering酸化によって芳香環に導き、ピニック酸化を経てカルボン酸へと誘導しました。
最後にアセトナイド部分を酸によって取り除くことで鮮やかな合成を示しています。
大村・砂塚らはその後、抗マラリア活性に特化した化合物の創出を目指し、大村天然物に基づいた抗マラリア薬の開発に向けた構造活性相関研究を行っています。[4]
これによりプベルル酸よりも高いマラリア活性を有し、in vivoでも効果のあった低毒性化合物を見出すことができています。
なお、一部報道において高いマラリア活性があるから毒性があるといった直接的な因果関係が書かれているものがありますが、これは正しいものではございません。
大村・砂塚らの研究のように高いマラリア活性を有しながら、in vitro, in vivoともに安全な化合物を創出することこそが創薬研究と言えます。
生合成経路
プベルル酸の全合成をご覧になった方や紅麹の菌がどのようにスタチン類の合成をしているかなどを考えていた方であれば当然プベルル酸の生合成が気になるかと思います。
筆者が探した限りですと現在においてプベルル酸そのものの生合成経路を詳細に提唱している文献はございませんでした。
一方で、別のトロポノイド類縁体の生合成について
(1)HPLCの分析などを用いて研究され、細菌による生合成を提唱している論文[5]
(2)13Cの取り込み実験を用いて真菌による生合成を提唱している論文[6]
がありました。
代表的なそちらの論文を2つ紹介させていただきます。
(1)Taoらの報告したHPLCの分析などを元に提唱した細菌によるトロポノイド類縁体の生合成経路[5]

Taoらの報告したHPLCの分析などを元に提唱した細菌によるトロポノイド類縁体の生合成経路(参考文献5より抜粋、編集)
実線部分は参考文献の筆者が分析実験によって実際に確かめている部分、点線はそれをつなぐべく提唱した部分となります。
一般にトロポノイドはフェニル酢酸から生合成されます。フェニル酢酸のベンゼン環がエポキシドへと酸化され、転位することにより7員環エノールエーテルへと導かれます。
その後、7員環エノールエーテルが加水分解されケトアルデヒドへと一度分解後、Knoevenagel縮合によって再閉環し7員環トリエンが生成すると考えられています。
その後トロポンへと変換され非ベンゼン系芳香族となります。以降は酵素によって酸化されることで各種酸化トロポノイドへと導かれるとのことです。
今回のプベルル酸はカルボキシ基を有しているため、さらに炭素数が多い状態です。後から炭素が入るのか、予め多い状態から今回ご紹介したような生合成されるかは定かではありません。
(2)Coxらが行った13C取り込み実験を用いた真菌による生合成仮説[6]

Coxらが行った13C取り込み実験を用いた真菌による生合成仮説(参考文献6より一部抜粋、編集)
次にCoxらの生合成仮説について説明します。
Coxらの提唱では先んじて7員環エーテルを経由しない経路が提唱されています。この経路では直接転位する経路と、先に記載したように開環する経路の2つがあり得ると考えられています。後者の場合ですと(1)とほぼ合流するような形になります。この経路ですとプベルル酸類縁体は予めベンゼン環上にはメチル基として取り込まれていて、最後にカルボキシ基に酸化されることを想定されています。
これらの情報と
(あ)さらに酸化されているプベルロン酸がプベルル酸と同時に単離されていること
(い)プベルロン酸が脱炭酸するとプベルル酸となることがわかっていること
を合わせて考えると、予めメチル基が2つ導入されていた(2)のような経路で進行し、(1)の終盤部分の酸化によってプベルロン酸が合成され、脱炭酸によってプベルル酸が生合成されていると予想できるかと思います。
みなさんも、ただいま紹介した生合成仮説から今回のプベルル酸がどのように生合成されているのか考えてみてはいかがでしょうか。
単離から構造決定までの歴史
最後に単離から構造決定までの歴史について述べます。
単離は冒頭で述べたように1932年に単離報告[3]があったのが最初となりますが、この時点では構造式はわかっていませんでした。
筆者は最初大村先生らの報告の時にさらっと構造が出てきていたのでどこで構造決定されたのだろうと不思議に思っていました。
調べてみる意外に歴史が深かったので別項目として下記にお示しします。
(どこまで詳細にかくか難しいですがあまり突っ込みすぎると歴史が深くなりすぎるので本記事では大枠の流れについて述べます。)
まず先述のように、1932年にBirkinshawとRaistrickらによって、P. puberulum Bainierが産生する化合物として単離されたところからプベルル酸の歴史が始まります。[3]
その後20年近くの間、芳香族化合物であるという実験結果は得られていたもののベンゼン環を持ったベンゼン系芳香族であると提唱され続けてきました。
ところが1950年にToddらは
分解実験を行った結果、生じている化合物が安息香酸誘導体になるはずであることに対し、これまでに報告されてきたヒドロキシ安息香酸誘導体どれとも合わないという実験事実に出会いました。
このことに加え、プベルル酸がその他の実験からフェノール性ヒドロキシ基が3つ存在すること、pHの情報、IRの情報などから、芳香族化合物であったとしても、ベンゼン環を有する化合物ではないのではないかと提唱しました。[7]
その後、連報の論文にて
(1)カルボニル基特有の反応性を示さない不活性なカルボニル基を持つこと
(2)臭素との反応において、付加生成物ではなく置換生成物が生成すること
(3)プベルロン酸から脱炭酸によってプベルル酸が生成すること
を加えて考えるとプベルル酸の構造は上記に示したような構造ではないかと提唱したようでした。
すなわち、この段階ではNMRを使わずに化合物の構造の特定に至っていたのです。
(それゆえにプベルロン酸はToddらが同時に構造提唱したのですが、この段階ではまだ構造が誤っています。)
X上ではあまりのNMRの単純さなどから、これはどのようにして構造決定されたのだと物議を醸していましたが、実はその構造決定はここに示したようなお話だったのです。
筆者的には意外な結末でしたが読者の方々にとってはいかがでしょうか。
本問題に関わる今後の展望
話を少し戻します。もしもプベルル酸が毒性の要因と特定された場合には、さらなる調査が必要になると考えられます。
生合成によって手に入れることができればそれでもよいですが、大量に必要な際にはご紹介した人工合成によって手に入れた化合物を用いることが期待できます。
今回の化合物が毒性の要因と決まってはいませんが、薬と毒は表裏一体、毒と薬は表裏一体(あえてひっくり返して2度書きます)ということを常に念頭に置く必要があり、人の体に作用するものを作る人たちは、混入するべき不純物がどのような作用を及ぼすのかについて調べ尽くす必要があります。
結び
最後に。
今回の分析に力を注いで原因究明をなさっている方、大変お疲れ様です。
また、何よりも被害者の方にお悔やみ申し上げます。
今後このような件が起こらぬことを心から望みます。
参考文献
- Sennari, G.; Saito, R.; Hirose, T.; Iwatsuki, M.; Ishiyama, A.; Hokari, R.; Otoguro, K.; Ōmura, S.; Sunazuka, K. Antimalarial troponoids, puberulic acid, and viticolins; divergent synthesis and structure–activity relationship studies. Sci. Rep. 2017, 7, 7259.
DOI: 10.1038/s41598-017-07718-3 -
Sennari, G.; Hirose, T.; Iwatsuki, M.; Ōmura, S.; Sunazuka, T. A Concise Total Synthesis of Puberulic Acid, a Potent Antimalarial Agent. Chem. Commun. 2014, 50 (63), 8715–8718. DOI: 10.1039/C4CC03134B.
-
Birkinshaw, J. H.; Raistrick, H. Studies in the Biochemistry of Micro-Organisms. Biochem. J. 1932, 26 (2), 441–453.
DOI: 10.1042/bj0260441. -
Saito, R.; Sennari, G.; Nakajima, A.; Kimishima, A.; Iwatsuki, M.; Ishiyama, A.; Hokari, R.; Hirose, T.; Sunazuka, T. Discoveries and Syntheses of Highly Potent Antimalarial Troponoids. Chem. Pharm. Bull. 2021, 69, 564–572.
DOI: 10.1248/cpb.c21-00132 -
Chen, X.; Xu, M.; Lu, J.; Xu, J.; Wang, Y.; Lin, S.; Deng, Z.; Tao, M. Appl. Environ. Microbiol., 2018, 84, e00349-18.
DOI: 10.1128/AEM.00349-18 - Davisona, J.; al Fahada, A.; Caib, M.; Songa, Z.; Samar, S.; Yehiac, S. Y.; Lazarusd, C. M.; Baieyd, A. M.; Simpsona, T. J.; Coxa, R. J. Genetic, molecular, and biochemical basisof fungal tropolone biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012, 109, 7642–7647.
- Corbett, R. E.; Hassall, C. H.; Johnson, W.; Todd, A. R. Puberulic and puberulonic acids. Part I. The molecular formula of puberulonic acid and consideration of possible benzenoid structures for the acids. J. Chem. Soc. 1950, 1950, 1–6.
- Corbett, R. E.; Johnson, W.; Todd, A. R. Puberulic and puberulonic acids. Part II. Structure. J. Chem. Soc. 1950, 1950, 6–9.