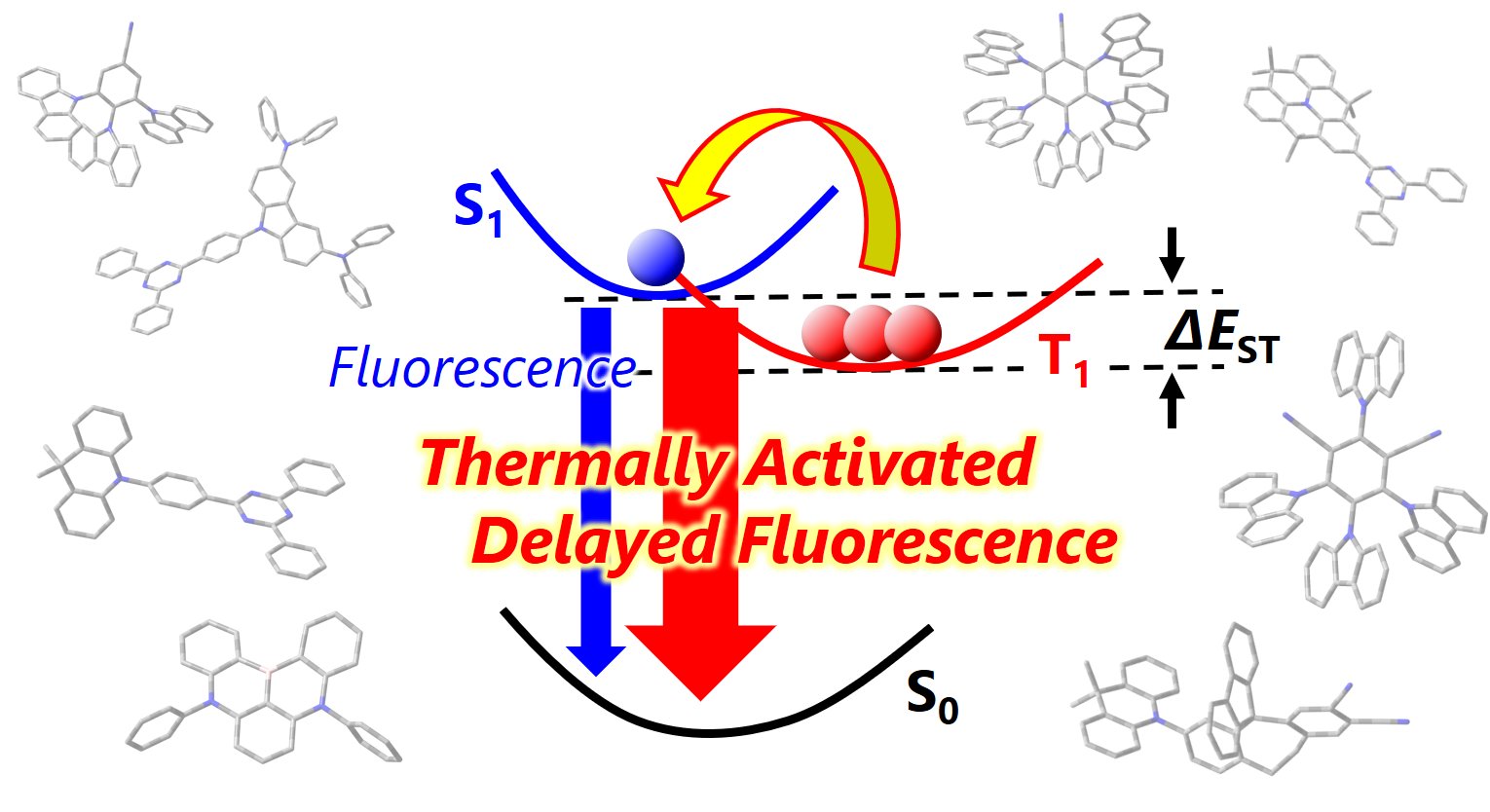複数の配位原子を持ち、それらを 2-3 原子程度離して持つような配位子は、金属原子を挟み込むように配位して安定な錯体を形成します。このような、多座配位子による安定な錯形成の効果をキレート効果といいます。
キレート効果の起源

上の反応について考えます。アンモニア錯体のアンモニアをエチレンジアミンで置換する反応です。アンモニアの場合もエチレンジアミンの場合も配位する原子は中性のアミン性 sp3 窒素であり、形成する金属-配位子結合の強さは似ていると考えられます。しかしこの反応は熱力学的に大変に有利で、反応は定量的に進行します。それはなぜでしょうか。
この反応の前後の分子の数に注目します。3つのエチレンジアミンで 6 つのアンモニア分子を脱離させるため、生成系の分子総数は原系の分子総数よりも大きくなります。このことは、生成系の方がエントロピーが大きいことを意味し、エントロピー増加が駆動力となって反応が進行すると言えます。実際に室温 (298 K) でのギブズエネルギー ΔG = ΔH−TΔS の内訳をみると、エンタルピー項 ΔH よりもエントロピー項 TΔS の方が大きいです (ΔG = ΔH−TΔS がより負に大きいほど平衡は生成物側に傾くことを思い出しましょう)。もしも新しい配位子がエチレンジアミンではなく、配位原子を1つしか持たない単座配位子であった場合は、6つの単座配位子で6つのアンモニアを置換することになります。その場合、反応系内の分子数は変わらないことになります。

キレート配位子による錯形成は、必ずしもキレート効果が駆動しているわけではありません。例えば遷移金属のヘキサアクア錯体の水分子をエチレンジアミンで置換する場合は、比較的弱い配位子である水を、より求核性が高い N 系配位子で置換できるため、そもそもエンタルピー的に有利な反応で、キレート効果の力を借りなくても進行するわけです。
キレート効果という名前の起源
キレート chelate という言葉はギリシャ語でカニのはさみを意味します。キレート配位子が金属イオンを挟み込む様子は、カニがはさみで金属イオンを挟んでいるようですね。

キレート効果の強さ
キレート効果の強さは配位原子の数、キレート性配位子の配位子原子の数、立体配座の自由度や配位原子の配置、あるいはキレート環の歪みに依存します。
配位原子の数
キレート性配位子の配位原子が多くなればなるほど、キレート効果は強くなります。これは、キレート効果が系の分子数の増加によって起こることから説明できます。すなわち、例えば2座配位子が金属に配位すると2つの単座配位子を遊離させることができますが、3座配位子ならば3つの単座配位子を遊離させることができ、生成系の分子数をさらに増やします。

立体配座の自由度
キレート性配位子が、あらかじめ金属をキレートするのに適した立体配座を持っていると、キレート効果は強くなります。

例えば2,2’-ビピリジン (bpy)とフェナントロリン (phen) を比較します。2,2’-ビピリジンはピリジン間をつなぐσ結合で回転できますが、キレート形成後にはその回転は自由度を失います。したがって、ビピリジンの立体配座の自由度は錯形成後に減少します。この立体配座の自由度の減少は、系中の分子数増加によるエントロピー増加効果を相殺し、キレート効果をやや弱めます。

遊離状態の bpy は σ 結合の周りで自由回転できます.

bpy がキレート形成すると配位子に立体配座が固定され, 自由度が減ります.
一方、フェナントロリンは金属をキレートするのに適した配座で固定されており、キレート形成前と後で配位子の自由度は変化しません。したがって、フェナントロリンはビピリジンよりも強いキレート効果を示します。とはいえビピリジンも優れたキレート配位子であることは事実なので、ビピリジンのキレート効果が小さいわけではなく、上記の説明はフェナントロリンがより優れたキレート形成を示す説明の一つとして理解しておくのがよいでしょう。

フェナントロリンは金属をキレートするのに適した配座にあらかじめ固定されているので, 強いキレート効果を示します.
ところで、上の項目で「配位原子が多くなればなるほど、キレート効果は強くなる」と書きました。この記述の上位互換として「キレート環の数が多いほどキレート効果が強くなる」と記述されることもあります。このような記述は、 3 座配位子であったとしても、キレート環を多く作れるような 3 座配位子の方がキレート効果を強く示す、と言っているのです。例えば、下に示す直鎖性の 3 座配位子 dien と冠型の3座配位子 tacn だと、冠型の 3 座配位子 tacn の方が強いキレート効果を示します。どちらも3座配位子ですが、直鎖性のdienはキレート環を2つしか形成しないのに対して、tacn は大きな環構造を持つためキレート環を3つ作ります。この理由も、後述される「立体配座の自由度」の観点から説明できます。すなわち tacn は遊離配位子の状態であらかじめ金属の配位に適した冠型の配座を取っており、キレート形成に伴う立体配座の自由度があまり変化しないのです。

環の歪み
キレート形成は、ときに歪んだ環を作り、エンタルピー的な負荷を与えます。例えば次の反応を考えます。

edta4- は6座性キレート配位子で、Medida2- は edta4- を中央のエチレン鎖でちょん切ったような構造を持つ三座配位子です。配位原子の数が多いほどキレート効果は強くなるという観点から、この反応は edta 錯体形成の方向に確かに進行します。しかしこの反応のエンタルピー変化を見ると、実は反応エンタルピーは正であり、この反応はエンタルピー的にはやや不利です。その理由は、edta4- はキレート形成するためには、配位子の立体配座をやや歪ませねばならず、キレート環自体もやや歪まなければならないからだと考えられます。上では edta4- と似た配位子を持つ Medita 錯体を用いて説明しましたが、[Mg(H2O)6]2+ など一部の金属アクア錯体からの edta 錯体形成もエンタルピー的に不利なことがあります。これらの例はキレート形成がエントロピー駆動の効果であることを示すと同時に、配位子に歪みが生じたり歪んだ環が形成される場合にキレート効果が弱くなることを意味します。

edta 錯体はキレート環に歪みを持っています.
キレート環の安定性は、おおまかに次のように整理できると知られています。

キレート環のおおまかな安定性. ただしキレート配位子の配位原子が炭素であることは意味していません.
すなわち、おおまかには 5 員環の形成が最も安定で、それよりも員数が大きくなったり小さくなるにつれてキレート環を作るのは不利になります。ただし、この順序はキレート環の原子の混成状態や金属イオンのサイズによっても変わるため、注意が必要です。もしキレート環の原子が sp2 混成軌道を持つ場合、6員環のキレート環も 5 員環キレートと同程度かそれ以上に安定になります。またキレート環の原子がsp3混成だったとしても、金属イオンが比較的小さい場合は5員環形成よりも6員環形成を好みます。
有名なキレート配位子とその略称



関連記事
- トランス効果 Trans Effects
- ヤーン·テラー効果 Jahn–Teller effects
- 【金はなぜ金色なの?】相対論効果 Relativistic Effects
- EDTA: 分子か, 双性イオンか
- 点群の帰属 100 本ノック!!
参考文献
- Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. Inorganic Chemistry, Pearson, Harlow, 2018, 5th edition.