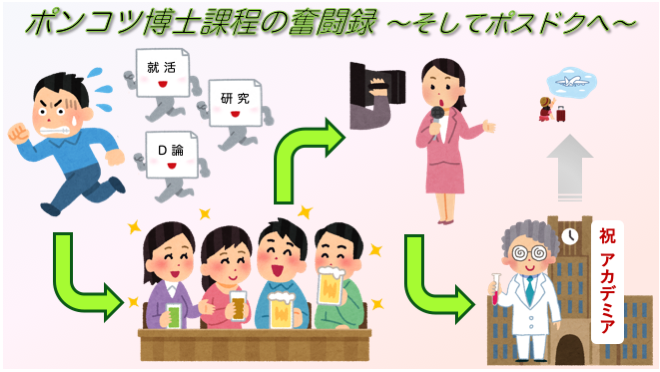bergです。ケムステをご覧の皆様の中には、小学生・中学生のお子さんをお持ちの親御さんもいらっしゃることでしょうか?夏休み真っ只中ということで、お子さんとのお出かけ先に頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、化学にまつわる博物館、独断と偏見に基づいていくつかご紹介したいと思います。
① 科学技術館
言わずと知れた東京を代表する博物館で、半世紀以上の歴史を誇ります。かの野依先生が館長を務めていらっしゃることでも有名ですね。
物理学や機械工学関連の展示が強いイメージのある科学技術館ですが、学生の夏休み期間に合わせて様々なイベントを開催しており、その中には化学に関するものも少なくありません。例えば、8/24(土)にはメルク株式会社 ライフサイエンスの協賛で「「化学発光を解き明かす」―ライフサイエンス研究ってなんだろう?小5~中学生編」が開催される予定です。
ほかにも、「「銅の日」イベント」や「科学の本「ブルーバックス」を親子で楽しもう!」など、興味深い催しが予定されていますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?
公式サイト:https://www.jsf.or.jp/
アクセス:東京メトロ東西線「竹橋」駅下車(1b出口) 徒歩約550m
東京メトロ東西線/半蔵門線/都営地下鉄新宿線「九段下」駅下車(2番出口) 徒歩約800m
入館料:大人950円、高齢者850円、中高生600円、こども500円
開館時間:9:30~16:50(入場16時まで)
② 越谷市科学技術体験センター(ミラクル)
越谷市科学技術体験センターは、2001年に開設された私立の科学館です。主に小学生向けの展示が施されており、夏休み期間には紫外線をテーマに蛍光などにまつわる体験実験も行っています。このほか、実験動画も多数公開しており、遠方の方でも楽しめる内容となっています。
公式サイト:http://www.miracle.city.koshigaya.saitama.jp/posts/menu2.html
アクセス:東武スカイツリーライン「新越谷」駅西口またはJR武蔵野線「南越谷」駅から徒歩10分
入館料:無料
開館時間:午前9時~午後5時
③ 千葉県立産業科学館
千葉県立産業科学館は産業へ応用された科学技術に関する展示に力を入れており、千葉県ゆかりのJFEスチールの高炉の模型や有数の規模のプラネタリウム、図書室までもを備えたユニークな科学館です。常設展示のほかにも液体窒素を使った冷凍実験と超電導の実験や高吸水性ポリマー、圧縮客家の実験などを実演しており、YouTubeでの配信も行っています。
公式サイト:https://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/exhibition/page-1518786538623/page-1518778482674/
アクセス:JR総武線・都営地下鉄新宿線「本八幡駅」下車 徒歩15分
入館料:一般:300円、高校生・大学生:150円
開館時間:9:00~16:30
④ 京都市青少年科学センター
関東圏ばかりに偏ってしまいそうなので関西の素敵な博物館をば。京都市青少年科学センターは小中学生等に対する理科教育のための科学館で、実際に物に触れ、体を通して体感し、科学を感覚的に理解でき、面白おかしく理科に触れ合えるような工夫が凝らされています。夏休みには液体窒素や磁性などをテーマにサイエンスライブの実演が行われており、必見です。
公式サイト:https://www.edu.city.kyoto.jp/science/thisweek/index.html
アクセス:京阪本線「藤森」駅下車,西へ約400メートル
入館料:一般520円、中高生200円、小学生100円
開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)
⑤ 国立天文台 野辺山
過去記事「化学系必見!博物館特集 野辺山天文台編~HC11Nってどんな分子?~」でも以前紹介させていただいた、長野県南牧村(みなみまきむら)に位置する「国立天文台 野辺山宇宙電波観測所」(通称;野辺山電波天文台)です。国立天文台(National Astronomical Observatory of Japan, NAOJ)は、核融合科学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所などとともに自然科学研究機構の中核をなす研究所の一つで、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などとともに日本の天文学、宇宙科学研究をリードしています。

45 mミリ波電波望遠鏡(筆者撮影)
長野県の高原という天体観測にうってつけの立地を生かし、巨大な電波望遠鏡がずらりと並んでいる景観は圧巻です。これらを用いて天体からの微弱なマイクロ波を検知し、宇宙空間に存在する星間分子の回転準位の遷移に相当する吸光・発光を検出し、同定につなげています。展示室内では、同天文台で発見された星間分子の分子模型が飾られており、大人でも楽しめること請け合いです。野辺山高原は北海道並みのきわめて冷涼な気候なので、昨今の猛暑を避けるにも絶好です。8/24(土)には特別公開も予定されているようですので、ご興味のある方は必見です。

複雑な星間分子(筆者撮影:HC9N、HC11Nなど)
公式サイト:https://www.nro.nao.ac.jp/
アクセス:JR小海線「野辺山」駅下車 徒歩2 km
・中央自動車道 長坂インターより清里道路を経て20 km
入館料:無料
開館時間:午前8時30分〜午後5時
せっかくの夏休み。化学を体感できる場所へ足を運んでみるのも良い過ごし方なのではないでしょうか。本記事が皆様のご参考になれば幸いです!