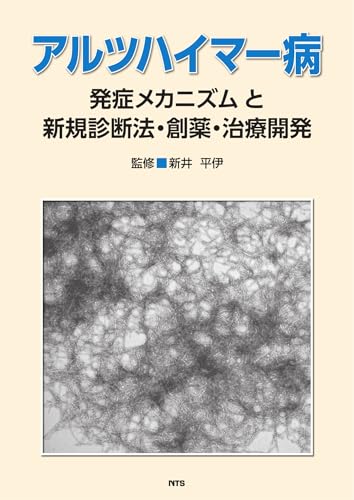第 619 回のスポットライトリサーチは、東京大学大学院 薬学系研究科 有機合成化学教室 (金井 求 研究室) に在籍されていた、古田 将大 (ふるた・まさひろ) さんにお願いしました!
金井研究室と言えばケムステ読者の皆様もよくご存知かと思われる有機化学研究のトップランナーでありますが、近年はさらに有機化学・触媒化学 x ライフサイエンスのシナジーを志向した新たな研究 (触媒医療) を展開されており、そちらの分野でも目覚ましい成果を挙げられております。特に有機分子触媒 (光酸素化触媒) を用いたアミロイドβ 分解薬の創成に関して眼を見張るものがあり、本サイトのスポットライトリサーチでも既に 2 回紹介させていただいております。
・アミロイド認識で活性を示す光触媒の開発:アルツハイマー病の新しい治療法へ
・触媒と光で脳内のアミロイドβを酸素化
アミロイドβはアルツハイマー病の原因とされる凝集タンパク質の一種で、アミロイドβを分解する抗体医薬「レカネマブ」が日本でも2023年に承認され、高い注目を集めましたが、その使用にはさまざまなハードルがあり、新機軸のアミロイドβ分解薬の創成が望まれています。
古田さんらの研究グループでは、これまでの触媒医療研究を踏襲しつつ、新奇な光酸素化触媒を見出し、さらにその毒性をプロドラッグ化 (ケージド化合物化) により抑制することに成功しました。ケージド化合物というと比較的大きな分子団を利用するイメージがありますが、本研究ではなんと一個の水素原子でケージド化合物化を実現するという驚くべき手法を利用しています。そして実際に in vivo でのアミロイドβ分解作用を確認し、アルツハイマー病治療に光明をもたらし得る新規低分子化合物の創成に成功しました。本研究の成果は高く評価され、Advanced Science 誌に掲載されるとともに、東京大学よりプレスリリースされました。
Leuco Ethyl Violet as Self-Activating Prodrug Photocatalyst for In Vivo Amyloid-Selective Oxygenation
本研究を統括された、有機合成化学教室 教授の 金井 求 先生より、古田さんについてのコメントを頂戴しております!
古田さんは、やると決めたことは何があっても最後までやり切る人です。学部・修士のときは、2017 年に当研究室で発表したヒストンアシル化触媒 DSH の活性を 100 倍上げてくれという私の無茶振りに、論理的で丁寧な触媒の構造変換を繰り返していましたが、結局、活性が下がったものしか取れませんでした。これは私も内心、才能ある彼の貴重な時間を潰してしまったと痛恨の思いで、今でも苦い思い出ですが、彼はもっと悔しかったと思います。博士に進学して、今度は 2021 年に発表したアミロイド酸素化触媒の活性を 100 倍上げてくれというテーマをお願いしました(なんと安直で反省がないことか!)。そうしたら今度は、基本構造を抜本的に変えた触媒候補を複数抽出して来て、それをもとに 200 倍活性の上がった触媒 EV を見つけてきました。しかし EV は細胞毒性が高く、どうする?と思っていたら、当研究室の隣の学生たちがやっている水素引き抜き触媒から発想を得たものと私は推測していますが、H でプロドラッグ化するという独創的なことを思いついて乗り越えて来ました。修士の苦い経験をプラスに転換する、古田さんじゃないとできなかった見事な学位研究だと思います。
それでは、インタビューをお楽しみください!
今回プレスリリースとなったのはどんな研究ですか?簡単にご説明ください。
社会の高齢化に伴い、アルツハイマー病の患者数は年々増大しており、社会問題の1つとなっています。しかしながら、その薬物治療は対症療法薬が主であり、レカネマブ等の抗体医薬を除けば根本治療薬は未だ存在せず、その開発が望まれています。
アルツハイマー病の発症メカニズムとして、アミロイドβ (Aβ) ペプチドの異常凝集がその発症に関与するという「アミロイド仮説」が提唱されています。この仮説を基に、これまで金井研究室では、光触媒による酸素化反応を利用することで Aβ の凝集性・毒性低減に成功していました。また、生体内反応への応用を見据え、血液脳関門 (BBB) 透過性を有する触媒の開発にも成功し、マウスを用いた実験において、静脈内投与と頭部への光照射による脳内Aβの光酸素化に成功していました (触媒と光で脳内のアミロイドβを酸素化)(1)。しかしながら、マウス脳内での本反応において① 触媒自体の反応性の低さ、② 頭皮組織に生じる外傷、という2点の課題を未だ残していました。
今回、我々は、これら課題を解決する新規光酸素化触媒 LEV を開発しました(2)。本触媒分子 LEV は、従来型触媒の200倍強力な活性本体 EV に水素原子を1個加えてケージングしたプロドラッグ体です。プロドラッグ化により、毒性・副作用の低減と脳への効率的な移行に成功し、マウス脳内での強力な反応を可能としています。
 |
Q2. 本研究テーマについて、自分なりに工夫したところ、思い入れがあるところを教えてください。
本研究にて思い入れがあるところは、触媒のプロドラッグ化およびそのメカニズム解明です。
EV を見つけた当初は、従来より 2 桁オーダー高活性であるのはよいものの、カチオン性分子のため脳移行性が悪く、また副作用・毒性も高く、改善が必要な状態にありました。藍建てのようにロイコ(還元型)色素をプロドラッグとして用いれば、組織中酸素により酸化されて活性本体であるEV を脳内で生成できるのではないかと発想し、LEV を合成しました。本分子は低毒性・高い BBB 透過性を示すことが分かり、設計通りの特性を発現させることができ嬉しく思いました。
 |
加えて、当初の発想とは異なり、酸素酸化によって LEV から EV へと変換されているのではなく、光を吸わないはずの LEV が光照射依存的に EV へと変換していることが実験で明らかになりました。そこから種々の機構解明実験を通して、自己触媒的に光照射によって活性本体 EV への変換が起こっていることを示すことができました。予想外の結果を得て大変驚いたことと、その解明をワクワクしながら試行錯誤して進めたことをよく覚えています。
Q3. 研究テーマの難しかったところはどこですか?またそれをどのように乗り越えましたか?
まず、高活性な触媒 EV を見つけ出すところに最も苦労しました。研究開始時は前報(1)の触媒の構造展開から始めたのですが、色々アプローチを試すもなかなか良いものが取れず 1 年半が経過しました。触媒骨格を変えるところから始めないと活性が大幅に上がらないのではないかと考え、闇実験でスクリーニングを開始し、トリアリールメタン系色素がよさそうだとわかったのは D2 の終わりの 2 月でした。これまでにないほど強力に反応が進行しているチャートを見て、MALDI の前で興奮に身体が打ち震えました。
また、そこから卒業までの残り1年間で細胞実験や動物実験を含めて、研究をまとめ上げる点にも苦労しました。やみくもに実験するのではなく、優先順位づけをすることを意識して効率的に研究を進めるよう心掛けました。動物実験に関しては、共同研究している富田研 (東大薬) の方々に手技を教えていただいたのですが、スケジュールを組んで繁殖させたり、投与実験したりと、有機合成の時間感覚とは違った難しさがありました。苦労しましたが、有機化学や光化学、生物学など多分野にわたる手技・知識を身に着け、一つの論文にまとめ上げることができたことを嬉しく思います。
Q4. 将来は化学とどう関わっていきたいですか?
私はもともと化学と生物学に興味があり、薬学部に進学しました。その中で金井先生の「自分にはヒトの体はフラスコに見える。生体内で起こっている反応は酵素という触媒が媒介している。人が作った触媒ならもっと凄いことができるはず」という触媒医療の概念に感銘を受け、6 年間研究を続けてきました。
現在私は製薬企業に勤務していますが、「有機化学に軸足をおきながら、生命現象を解明し、さらに介入する」という考えは変わりません。本研究のように、周辺領域を取り入れながら研究を進め、創薬研究を通じて社会貢献に努めたいと考えています。
Q5. 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします!
最後までお読みいただきありがとうございました。前述の通り、本研究はなかなか結果の出ない期間がありました。苦しいながらも研究を楽しみ、常に手を動かして次の一手を探し続け、かつチャンスが来たら逃さない心積もりをしていたことが今回の結果につながったのかなと感じております。
また、高校生のころから拝見していた Chem-Station で、自身の研究を取り上げていただき、大変嬉しく感じます。このような光栄な機会を与えていただきました Chem-Station の皆様に感謝申し上げます。
最後になりますが、いつもご指導・ご助言を賜り、研究遂行を支援くださいました金井 求 教授、川島 茂裕 准教授、三ツ沼 治信 助教をはじめとする金井研の皆様に深く感謝申し上げます。また、共同研究してくださいました和歌山県立医科大 相馬 洋平 教授、東大 富田 泰輔 教授、堀 由起子 准教授、京大 梶 弘典 教授、志津 功將 助教に感謝申し上げます。
参考文献
(1) Nagashima, N.; Ozawa, S.; Furuta, M.; Oi, M.; Hori, Y.; Tomita, T.; Sohma, Y.; Kanai, M. “Catalytic photooxygenation degrades brain Aβ in vivo” Sci. Adv. 2021, 7, eabc9750. DOI: 10.1126/sciadv.abc9750
(2) Furuta, M.; Arii, S.; Umeda, H.; Matsukawa, R.; Shizu, K.; Kaji, H.; Kawashima, S.A.; Hori, Y.; Tomita, T.; Sohma, Y.; Mitsunuma, H.; Kanai, M. “Leuco Ethyl Violet as Self-Activating Prodrug Photocatalyst for In Vivo Amyloid-Selective Oxygenation” Adv. Sci. 2024, 2401346. DOI: 10.1002/advs.202401346
研究者の略歴
名前:古田 将大 (ふるた まさひろ)
所属 (研究当時):東京大学大学院 薬学系研究科 有機合成化学教室 (金井 求 研究室)
研究テーマ:生体レベルでの応用を志向した高活性アミロイド光酸素化触媒の開発研究
略歴:
2018年3月 東京大学 薬学部 薬科学科 卒業
2019年4月-2023年3月 東京大学生命科学技術国際卓越大学院プログラム (WINGS-LST)
2020年3月 東京大学大学院 薬学系研究科 薬科学専攻 修士課程 修了 (指導教員: 金井 求 教授)
2020年4月-2023年3月 日本学術振興会特別研究員(DC1)
2023年3月 東京大学大学院 薬学系研究科 薬科学専攻 博士課程 修了 (指導教員: 金井 求 教授)
2023年4月- 製薬企業研究員として勤務

古田様、金井先生、インタビューにご協力いただき誠にありがとうございました!
それでは、次回のスポットライトリサーチもお楽しみに!
関連動画: 金井 求 先生のケムステVシンポご講演動画
金井研のスポットライトリサーチ
・無保護糖を原料とするシアル酸誘導体の触媒的合成
・アミロイド認識で活性を示す光触媒の開発:アルツハイマー病の新しい治療法へ
・トリプトファン選択的なタンパク質修飾反応の開発
・可視光エネルギーを使って単純アルケンを有用分子に変換するハイブリッド触媒系の開発
・触媒と光で脳内のアミロイドβを酸素化
・タンパク質機能をチロシン選択的な修飾で可逆的に制御する
・細胞内で酵素のようにヒストンを修飾する化学触媒の開発
・保護基の使用を最小限に抑えたペプチド伸長反応の開発
関連書籍
医学のあゆみ アルツハイマー病――研究と治療の最前線 2023年 287巻13号 12月第5土曜特集[雑誌]


![医学のあゆみ アルツハイマー病――研究と治療の最前線 2023年 287巻13号 12月第5土曜特集[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/411sRs4TdOL._SL500_.jpg)