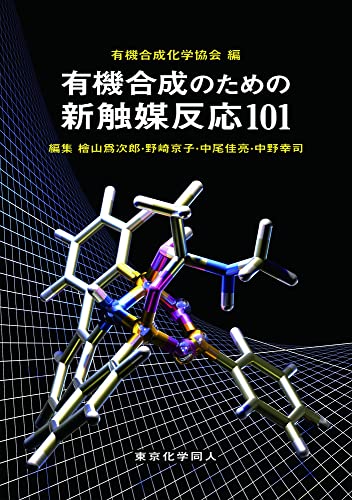第402 回のスポットライトリサーチは、大阪大学大学院薬学研究科の 岡 直輝 (おか・なおき) さんにお願いしました。岡さんは、岐阜薬科大学 創薬化学大講座 薬品化学研究室 (佐治木 弘尚 教授) の特別研究学生として研究を行なっておられます。
今回、岡さんらのグループは鈴木-宮浦カップリング反応などで汎用されるボロン酸エステルの新規かつ安定な誘導体を開発しました。ハンドリングの容易なこの新規誘導体の有用性は高く評価され、Organic Letters 誌のカバーに採用されたほか、論文発表より2ヶ月あまりで、1年間で最も読まれた Organic Letters 誌の論文第 1 位 にランクイン (令和 4 年 7 月 11 日現在)し、さらに全科学研究論文の TOP5%に入るオルトメトリックスコア 95 を得る (令和 4 年 7 月 2 日現在) など、非常に高い注目を集めています。
【2025/10/18 追記】本論文が、2022〜2023年における日本人著者の Organic Letter 誌掲載論文の中から highly cited article の一つに選ばれたとのことです (井川研 X より)。おめでとうございます!
Aryl Boronic Esters Are Stable on Silica Gel and Reactive under Suzuki–Miyaura Coupling Conditions
Naoki Oka, Tsuyoshi Yamada, Hironao Sajiki, Shuji Akai*, and Takashi Ikawa*
Org. Lett, .2022, 24(19), 3510–3514, DOI: 10.1021/acs.orglett.2c01174A wide range of aryl boronic 1,1,2,2-tetraethylethylene glycol esters [ArB(Epin)s] were readily synthesized. Purifying aryl boronic esters by conventional silica gel chromatography is generally challenging; however, these introduced derivatives are easily purified on silica gel and isolated in excellent yields. We subjected the purified ArB(Epin) to Suzuki–Miyaura couplings, which provided higher yields of the desired biaryl products than those obtained using the corresponding aryl boronic acids or pinacol esters.
本研究を指揮された、岐阜薬科大学 創薬化学大講座 薬品化学研究室 准教授 (2025年現在・同大学アドバンストケミストリー研究室 教授)の 井川 貴詞 先生より、岡さんの人となりについてのコメントを頂戴しております!
岡君は、まるで子供のように好奇心旺盛で、周りの学生たちを巻き込みながら毎日楽しそうに研究に取り組んでいます。今回、取り上げて頂いた研究テーマも岡君の遊び心からスタートしており、彼がいなければ今回の研究成果は出せなかったと断言できます。純粋な好奇心と鋭い観察眼は彼の天性のもので、優秀な研究者になるための資質を兼ね備えていると思います。学位取得後は、日本の将来を担う薬学研究者(Pharmacist-Scientist) として大きく羽ばたいてくれるものと確信しています。
それでは、インタビューをお楽しみください!
Q1. 今回プレスリリースとなったのはどんな研究ですか?簡単にご説明ください。
ボロン酸は鈴木カップリングの基質として有機合成に広く利用されています。なかでも、芳香族ボロン酸のピナコールエステル [ArB(pin)] は、反応性と安定性のバランスが優れており、現在最も汎用されるボロン酸誘導体として知られています。ArB(pin) の重要な特徴の一つとして、シリカゲルカラムによる精製が可能である点が挙げられます。しかし、その精製には豊富な知識と経験が必要で、上手く扱わないと収率が極端に低くなります。
今回、私たちは ArB(pin) が有する 4 つの Me 基を Et 基に変更するのみで、誰でも簡単に扱える新たなボロン酸エステル ArB(Epin) を開発しました。「ArB(Epin) は Et 基末端の Me 基がホウ素の空軌道を動的に保護する適切な距離にあるため、ボロン酸誘導体を安定性化しつつ、反応性を維持することが可能」という仮説に基づき、設計・開発しました。
ArB(pin) を薄層クロマトグラフィー (TLC) 上にスポットして展開すると、必ずと言っていいほど原点に吸着された化合物が残ります。また、テーリングが酷くシリカゲルに対する親和性が極めて高い化合物といえます。一方、ArB(Epin) は原点に残らない上に全くテーリングせず、綺麗なスポットとして化合物が観測されました (図1の左側)。この TLC 上での挙動は、そのままカラム精製の結果として現れ、ArB(Epin) は通常の化合物と同様にシリカゲルカラムによる精製を行ってもほとんど収率が低下しません。また、ArB(Epin) はそのまま鈴木カップリングへと適用可能であり、クロスカップリング反応によって収率よくビアリール類を合成することができました (図1の右側)。また、興味深いことに、ArB(Epin) を用いたとき、対応するボロン酸[ArB(OH)2]や ArB(pin) を原料とした場合よりも高収率を与えました。

図1 開発した ArB(Epin) の特徴
Q2. 本研究テーマについて、自分なりに工夫したところ、思い入れがあるところを教えてください。
全くテーリングしていない TLC を初めて確認した瞬間を今でも鮮明に記憶しています。私は TLC 上で ArB(pin) がテーリングを起こしたり、カラム精製によって ArB(pin) の収率が大幅に低下したりする実験を何度も経験していたので、「自分と同様にボロン酸誘導体を扱う多くの研究者が ArB(pin )の扱いに困っているに違いない」と問題意識を持っていました。ただ、あまり凝ったことをして問題を解決しても誰も使ってくれないと思い、考え方をできるだけシンプルにして今回の保護基を設計しました。
Q3. 研究テーマの難しかったところはどこですか?またそれをどのように乗り越えましたか?
正直なところ、本研究の魅力を分かりやすく伝えること、そして、研究自体を継続する事に結構なエネルギーを使いました (苦笑)。これまでに多くの実績を有する ArB(pin) からの変更点が「Me 基を Et 基に変えるのみ」と、あまりにシンプルだったために、ラボ内からもテーマの継続を不安視する声が多く聞かれました。もちろん、自分ではテーマを信じて続けていましたが (半分、心が折れていました)、学会で発表した際、「是非、使ってみたいので、ArB(Epin) の合成法を教えてほしい」など数名の先生方や学生さんにお声がけ頂いたことがすごく心に響きました。最終的には、論文がアクセプトされ、世界中から多くの反響を頂けるようになって、「この研究を辛抱して続けて良かった」と心から思えるようになりました。
Q4. 将来は化学とどう関わっていきたいですか?
学位取得後は創薬関連の面白い研究をしたいと漠然と考えています。私はこのまま順調にいけば、6年制の薬学部を卒業した薬剤師博士 (ファーマシスト・サイエンティスト) になります。薬剤師免許を直接、使用する機会は少ないかもしれませんが、薬学に関連する知識を生かした創薬研究を推進すれば、新しいことができると信じています。
Q5. 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします!
研究結果を論文として形にできたのは、ご指導頂いた研究室内外の諸先生方や悩み多き私を勇気付けてくれた先輩方、後輩たちのお陰と感謝してもしきれません。みなさんも、様々な縁を大切にし、感謝の気持ちをもって研究に励みましょう。
研究者の略歴
名前:岡 直輝 (おか なおき)
所属:大阪大学大学院 薬学研究科
専門:有機化学
略歴:
2020年 大阪薬科大学薬学部薬学科 (現 大阪医科薬科大学) 卒業
2020年– 大阪大学大学院薬学研究科 (2022年現在 博士課程3年在学中)

岡さん、井川先生、インタビューにご協力いただきありがとうございました!
それでは、次回のスポットライトリサーチもお楽しみに!
関連動画: 佐治木先生のケムステVプレミアレクチャー
関連記事: 井川先生のご研究のスポットライトリサーチ
・立体障害を超えろ!-「London分散力」の威力-
・位置・立体選択的に糖を重水素化するフロー合成法を確立 ― Ru/C触媒カートリッジで150時間以上の連続運転を実証 ―