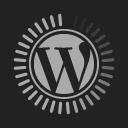さて、今回の記事でラストとなりますが、前回に引き続いて、「エバポ用真空制御装置の自作」に挑戦していきます。前回までの記事では、圧力センサ、液晶ディスプレイ、ロータリエンコーダ、電磁弁を接続し、真空制御装置の試作機を完成させました。本記事では、それらをケースに収める方法をおおまかに説明していきます。
注意:ケースに収めるために、ボール盤などの使い方を誤ると重大な事故につながる可能性のある道具を使います。これまでの記事のようなArduino/ブレッドボードを用いる工作は、基本的に、はんだごてを少し使う程度であり、経験が少なくてもハードルはそこまで高くないものでした。しかし、今回の記事ではケースに穴をあけるなど初心者には難しい内容が含まれています。そのためボール盤などを用いた工作の経験がない方の場合は、前回の記事で作った試作機をタッパーなどのケースに収めるにとどめておき、今回の記事は参考程度に読んでいただくことをお勧めします。また、今回の記事ではおおまかな流れを説明するにとどめ、細かい部分は省いています。挑戦する場合、臨機応変に対応してください。
パーツ集め
まず、必要なパーツを挙げます。前回までの記事で用いた圧力センサ、液晶ディスプレイ、電磁弁などのパーツは省略し、今回から新たに必要になるものだけを挙げています。液晶ディスプレイに関しては、はんだ付けしたピンソケットを外すよりも新しいものを調達した方が楽かもしれません。ねじ等の細かいパーツは詳細を指定していません。最適なものをホームセンターなどで手に取りながら選んでください。
・ドライバ内蔵リレーモジュールキット 2キット (秋月電子通商、 通販コード: K-13573)
※今回は、小型化のために前回用いたリレーボードよりもコンパクトなリレーキットを用いることにしました。含まれているリレーそのものは全く同じですが、ドライバ回路が大幅に小さくなっています。
・片面ガラス・ユニバーサル基板(ブレッドボード配線パターンタイプ) 1枚 (秋月電子通商、 通販コード: P-04303)
・耐熱電子ワイヤー 1m×10色 導体外径0.36mm(AWG28相当) 1パック (秋月電子通商、 通販コード: P-11640)
・防水形トグルスイッチ Mシリーズ M-2011W 1個 (モノタロウ、注文コード: C38445251)
・トグルスイッチ用ON-OFF文字板 AT-211 1個 (モノタロウ、注文コード: C49020867)
・防水形押ボタンスイッチ Mシリーズ MB-2011W 1個(モノタロウ、注文コード: C08600435)
・押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) 黒色 AT-413-K 1個 (モノタロウ、注文コード: C49020982)
・SPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックス SPCP131804T 1個 (モノタロウ、注文コード: 88226083)
・RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RM8L-4B 4個 (モノタロウ、注文コード: 88365435)
・サドルバンド 1個
※圧力センサをケースに固定するために使います。ホームセンターでパイプなどを固定するために販売されているものの中から最適な大きさのもの選びました。
・ねじ、六角ナット 数セット
※Arduinoや液晶ディスプレイ、メイン基板をケースに固定するために使います。ホームセンターで最適な太さ、長さのものを選びました(今回は太さM2.6あるいはM3、長さは15 mmあるいは25 mmのねじを使用)。また、装置をスタンドやエバポに固定するための太めのねじを一本使いました。
・ムッフ 1個
※装置背面の太めのねじを挟んでエバポ本体やスタンドに固定するために使います。
・スペーサー M3×2 mm 4個 (共立エレショップ 商品コード: E5G41B)
※Arduinoボードをケース底面から2 mm浮かせて取り付けるために使います。
・スペーサー M3×10 mm 6個(共立エレショップ 商品コード: 5C3257)
※液晶ディスプレイとメイン基板をケース底面から10 mm浮かせて取り付けるために使います。
必要な工作機械
・卓上ボール盤
大学の工作センターなどにもあります。ホームセンターには普通の電気ドリルをボール盤として使うための台も売られていますが、安定性などの問題からおすすめはできません。監督者がおり、指導が受けられる大学等の工作センターでの利用をお勧めします。
装置をケースに収める
ケースに収める前にまず、ブレッドボードやジャンパワイヤをユニバーサル基盤や導線に置き換えて抜けないようにはんだ付けします。そのためにまず、Arduinoのピンソケットを外します。
A.これが正しいやり方かどうか怪しいですが、無理やりArduinoのピンソケットを外して導線を直接ボードにはんだ付けできるようにします。市販のArduinoをこのように改造するよりも、自分でArduino互換ボードを作った方がよいかもしれません。そちらの方がソケットを外す手間は省けますし、費用も抑えられると考えられます。まず、図のようにピンソケットをニッパーで2ピン単位ごとに切断し、その後それらをラジオペンチで抜いていきます。そうすると中の金属部分が露出するので、裏面からはんだ吸取器などを用いてこのピンもはずします。
B. ピンソケットを外した後のArduinoボードの画像を図Bに示します。GNDのピンははんだごての熱が逃げやすくなっているため外すのに苦労するかもしれません。
C. ブレッドボード配線パターンタイプのユニバーサル基盤に、前回までの記事で試作した装置を参考にして同じ回路となるように電子部品を配置し、はんだ付けします。そして、このメイン基板とArduino、液晶ディスプレイなどとをジャンパワイヤを用いずに、直接導線を基盤にはんだ付けすることによって接続します。その際には図のように万力やクリップを用いてArduino、メイン基板、液晶ディスプレイを固定すると作業しやすいです。今回は前回までとは異なるリレーキットを用いていますが、小型化されている以外は変わりません。秋月の商品ページの回路図を参考に同様に配線してください。前回までに用いたリレーキットを用いても全く問題ありませんが、メイン基板にリレーを載せた方がすっきりするため今回は小型のリレーキットを採用しました。
D. 次に、卓上ボール盤を用いてケースに穴をあけます。どこにどの大きさの穴をあけるかは、パーツをどのように配置するか考えて決めます。今回用いたケースには邪魔な突起が内側に8個あったので、これをまず削り取りました。写真のようにクランプなどを用いてケースをしっかり固定してから作業します。卓上ボール盤使用時は、巻き込み事故を防止するため手袋、軍手の使用は厳禁といった注意事項がいくつかあるので工作センターの監督者の指示に従ってください。
E. ケース内部の突起の削り取りと穴あけが完了したときの写真です。左側側面のUSBケーブルを挿す部分は、穴をあけた後にやすりで削ることで四角形に整えました。真ん中の大きな穴は装置をスタンドなどに固定するための太めのねじを通す穴です。右と手前側面の大きな4つの穴は、ケーブルグランドをはめるための穴です。ここからACアダプタ、圧力センサ、電磁弁につながるケーブルを出します。
F. 穴あけが完了したケースにパーツをねじを用いて固定した後の様子を図Fに示します。いずれの部品もスペーサーを間に入れてケース底面より2 mm あるいは10 mm浮かせてケースにねじ止めしました。Arduinoボード、液晶ディスプレイ、メイン基板上にはんだ付けした導線の根本は曲げに弱いのでホットボンドで補強しておきます。この後、全面パネルに穴あけを行い、スイッチ、ロータリエンコーダを固定し、そのパネルをケースに固定すれば完成です。
動作確認
完成した装置のACアダプタをコンセントに挿し、電源スイッチをONにした時の装置の前面と背面の画像を載せます。
以下は、エバポにつなげた後の画像です。装置裏面の太いねじ部分をムッフで挟むことによってエバポ本体に固定しました。酢酸エチル/ヘキサン混合溶媒をスピーディーに留去することができました。バルブ、コックを用いて手動で圧力をコントロールする場合には一台のダイアフラムポンプに複数台のエバポを接続してしまうと、互いの影響が出てしまうため、効率が下がってしまうことがありました。しかし、今回製作した装置を用いた場合は一台のポンプに複数台のエバポをつなげた場合でも、常に自動で調節してくれるため、ダイアフラムポンプの節約と実験効率の維持を両立できるかもしれません。
おわりに ~研究室でのIoTの実現に向けて~
以上で連載記事「研究室でDIY!~エバポ用真空制御装置をつくろう~」は終わります。後半になるほど細かい作業が多く、特に今回の記事⑤に関しては、卓上ボール盤を使うなどかなりチャレンジングな内容となっていますが、記事①、②に関しては部品さえ集めることができれば誰でも挑戦しやすい内容となっていますので、挑戦してみてください。書籍「Arduinoをはじめよう」などを参考に、LEDをチカチカ光らせるだけでも楽しめると思います。
Arduinoにイーサネットシールドと呼ばれるユニットを接続するとインターネットに接続することもできます。そうすると、測定値をどこからでもリアルタイムで確認することができるようになります。IoTという言葉が世間では注目を集めていますが、私はArduinoが研究室でのIoTの実現に役立つと考えています。今回紹介したエバポ用真空制御装置はArduinoでどんなことができるかを示すための一例にすぎません。圧力を制御するという枠にとらわれずに、自由な発想に基づいて新たな装置、システムの開発に挑戦してみてください。近年、Raspberry Pi(ラズベリー パイ)とよばれるものも注目を集めています。興味ある方はこちらも手に取って利用してみてください。
最後になりましたが、一連の内容を記事にするにあたり多大な協力をしてくださいました山口潤一郎先生、このようなさまざまな挑戦を見守ってくださるとともに日頃からあらゆる面でお世話になっている鳶巣守先生、雨夜徹先生、兒玉拓也先生、後輩を含めた研究室のメンバーの皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。
免責事項:一連の記事に掲載された情報、道具、試作した機器を利用することによって発生した人的、商的、および財産的損害などに関して、当方は責任を負いかねますので、あくまで技術的資料として参照し、利用者の責任においてご利用ください。
研究室でArduinoを使うにあたり、役立つ書籍が数多く出版されています。Webページからも多くの情報を得ることはできますが、書籍からのほうがより詳しい情報を得やすいかもしれません。
関連書籍
[amazonjs asin=”487311733X” locale=”JP” title=”Arduinoをはじめよう 第3版 (Make:PROJECTS)”]※①の記事でも紹介しましたが、初めてArduinoを使う方におすすめの一冊です。プログラムに関しても優しく書かれています。
[amazonjs asin=”4789842193″ locale=”JP” title=”Arduinoで計る,測る,量る: 測定したデータをLCDに表示,SDカードに記録、無線/インターネットに送る方法を解説 (マイコン活用シリーズ)”]※計測したデータをLCDに表示、SDカードに記録、無線/インターネットに送る方法を解説。
[amazonjs asin=”4789846733″ locale=”JP” title=”研究室で役立つ パソコン計測アナログ回路集(TRSP No.133) (トランジスタ技術SPECIAL)”]エバポ真空制御装置を作ろうシリーズ
- 部品の大まかな説明、マイコンについて、また必要なパーツを集め
- 圧力センサの信号をパソコンに転送。ハードウェア編とソフトウェア編
- 液晶ディスプレイを接続し、それに表示する方法
- 全部接続してみよう
- 組み立てて動かしてみよう(本記事)
本記事は、大阪大学鳶巣研究室の櫻井駿さん(博士課程3年)による寄稿記事です。