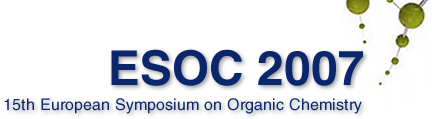Tshozoです。安価で活性の高い触媒を見出した前回のつづき、早速いきます。
(2)産業界との連携-1 鉄鋼メーカとの連携
本書と順番は違うのですが記述量の関係から先にこの点を(Holdermann本では、(1)触媒探索の後は高圧リアクター開発のことを書いています)。
アンモニア合成パイロットプラント立上げに伴い様々な計器類や配管類が必要になったのですが、Bosch本人がどれだけ鉄系材料に精通していたとしても製造はBASFだけでは何ともしがたいものばかり。また従来使用環境と違い高圧がかかったり腐食が激しかったりで、特に高圧環境下における金属水素化(≒金属の脆性化)を出来るだけ防ぐことの出来る特殊鋼が必要になってくることがわかっていました。
そこでBoschは当時最大の製鉄会社であったティッセン(Duesseldolf)とクルップ(Essen)にそれらのニーズをぶつけます。この2社はのちに合併し現在も世界的巨大鋼鉄メーカ(ThyssenKrupp)ですが、元々「鉄と血」の片棒を担ぐ軍需会社の色合いが強かった状態でした。その軍需産業の中で間隙を縫って供給されたニッケル合金が非常に腐食に強く、強度も非常に高い状態を保ち、この高圧水素へ向いた合金であることが判明した・・・!!!

ティッセンとクルップの当時の社章 デザインがやっぱりカッコいい
スタートレックのマークはThyssenのマークを参考にしてそう
・・・だとカッコいいのですが、実はこの試みは当初失敗します。Boschは当時最先端の金属組成学も修めており鉄鋼2社の開発状況も詳しく理解していたため上記のニッケル合金が適しているという推論に至りましたが、ニッケルを合わせただけではあんまり高圧水素に対して適していない(ungeeignet)ことがわかりました。しかしそこで諦めないのが我らがBosch。両社に直接乗り込み、一時期は2社での開発を進める時間がBASFの作業場滞在時間よりも長くなるほど新金属創出に入れ込みます。
その際彼はニッケル合金をもとにして開発を進め、遂にわずかのクロム、モリブデン、タングステンが混ざった高耐久合金が高圧水素にも十分に耐えうることを発見します。この合金は今で言うステンレス、インコネルといったような耐食合金・超高耐食合金の奔りでもあり、ドイツの特殊鋼技術レベルの下押しに貢献した形になります。
もちろんこれらはあくまで一例で、アンモニア合成にかかわる金属開発は部下たちにより様々に実施されていました。つまりティッセンとクルップにおける特殊鋼やステンレスの実用化と充実した合金類のラインナップはのBoschの開発を支えるために誕生したと言っても過言ではないのです![裏付け:文献1]
 BASFで開発最初期に導入された、ごぞんじアンモニア高圧リアクター
BASFで開発最初期に導入された、ごぞんじアンモニア高圧リアクター
筆者の友人がハイデルベルグ Carl Bosch Museum(リンク)で撮影
ティッセンとクルップ、2社の協力無くしては実現しなかった
・・・というのは言い過ぎかもしれませんが(軍需がありましたので)、実際2社がステンレス工業化に成功した時期はBoschの開発時期と重なります。日本製鉄殿(リンク)のある講演で聞いた話では、この2社のステンレス特許が出て生産を本格的に開始したのは1913年でしたから、この生産準備時期がアンモニアのリアクター開発(次回参照)の時期と一致しますね。またこの後も肥料や火薬の原料である硝酸に耐食性を持つ新ステンレス合金も同時に発明され、望むと望まざるとに関わらずドイツの軍需を支える重化学工業の基礎が出来上がっていきます。
この2社は最終的に鉄鋼版I.G.ファルベン、”Vereinigeten Stahlwerke”となるわけですが、この社長であったナチスのAlbert Voeglerは色々あったにせよBoschのことを激賞していましたから、鉄鋼業界への彼の貢献の大なることは周知が認めるものであったのでしょう(この激賞をBoschが文字通り受け取ったかは微妙な時期であったため、ちょっと疑問がのこりますが・・・ドイツの鉄鋼業界紙”Stahl und Eisen”が1940年にBoschのために追悼文を書いていたくらいですからまぁ間違いないと思います)。
(2)産業界との連携-2 ジーメンスなどとの連携
鉄に関する開発と並行して同時期にBoschは反応前ガス昇圧にメンテフリーで使用でき、厳密な軸シールは必要としつつもさほど精度を必要としないタイプの”Maulwurfpumpe「もぐらポンプ」”、今で言う封止型遠心ターボポンプを開発します。当時はモータ→シャフト→シール→遠心昇圧用インペラ、というようにシールを介して外にモータがあるタイプが多く、高圧になるとシール部からガス漏れが多発していました
そこでBoschはここでも発想をはたらかし、「モータごと遠心分離機の内部に入れて動かしてやるような形にすればシールも楽になるはず」という考えのもと下の写真のような遠心昇圧ポンプを考案します。

筆者の友人がHeidelbergのCarl Bosch Museumで撮影した「もぐらポンプ」
中央円筒部に高速モータが「もぐら」のように設置されており、シールを介して
両端部のインペラを回していた形式・・・のはず 記憶が少し怪しいですが
これにより回転部シールの負荷が軽減されモータ配線部のシールに集中できる
これで高圧リアクタ手前の昇圧を容易に行うことが出来るようになったのですが、モータ開発に関わった当時重工業の雄ジーメンスの開発トップであったゲオルグ・ジーメンスに至ってはこの装置を”なんでかわからねえけどうまく動きやがるんだ!”と不思議がっていたようですが・・・。(注:現在では高度な機械加工ができるようになったため、このモータごと装置に放り込むようなタイプは使われていないようです・現在の構成はたとえば荏原制裁所殿のHPなどを参照のこと)。

現代の一般的な昇圧遠心ターボポンプの構造例(図は英語版wikiより引用)
モータが外側に付いており、赤線〇部のシールが内部の圧力封止レベルをきめる
回転数に応じてギアボックスが付いたり付かなかったり
(Boschのもぐらポンプはモータ、カップリングごと円筒に封じ込めている形)
さらに、空気中からの窒素分離に利用された深冷分離法を開発したリンデ(Linde:会社HP)は当時既に洗練された冷却技術を持っており、空気の冷却による純窒素の精製の部分で本件に貢献しています。ただこれはアンモニア合成のために開発された技術ではなく、もともと飲料を冷やす技術を改良したもので間に合ったのですが、商売上でLindeがこうした化学工業へ応冷却器を用する足掛かりを作ったという、新規開拓の好例であったとも言えるのではないでしょうか。
一般的にドイツ重工業と言えばメッサーシュミットやハインケル、ベンツやポルシェやBMWといった完成品・完成車メーカが代表的なアレですが、こうした金属系の素材や周辺技術についても当時の時点から世界トップを走っていたわけであり、その技術力を更に掻き立てる原動力として業界を牽引していたのはこのBASFにおけるBoschによるぶっ飛び開発だったというのも興味が尽きないところです。
こうやって見てくるとアンモニア工業化はおそらく化学業界ではじめて、異業種の総力も結集して行われた複合イノベーションの原型であったとも言えるのではないでしょうか。またこれはどこかの国がやってるような計画経済的に国家が率先した「ように見せる」ものでなく、自由な研究活動の場である大学で、Haberが創製した技術のタネをBrunckの経営判断に基づいた心理的バックボーンに基づきBoschがリーダとして活躍し、それをMittaschらの個々の要素技術が力強く支えたという、真に健全な民間での技術開発の成功モデルとなったわけです(結論として言うにはまだ早いですが)。
それでは今回はこんなところで。次回はいよいよ核心の高圧リアクターのところを書きます。
→”その7“へ