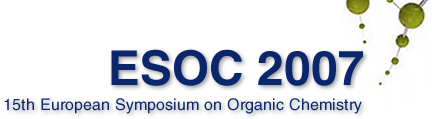前回、有機反応を俯瞰するということで反応を1つとしてみるだけでなく、遠くから眺めてみようということでシグマトロピー転位について解説しました。今回は転位反応の第 2 弾ということで、アルキル基がすぐ隣の原子に移動するタイプの反応について、横断的に見ていきます。転位の形式で言えば、σ 結合が下の図のように移動するので、 1,2-転位ということになります。

具体的には、ピナコール転位、 Beckmann 転位あるいは Baeyer-Villiger 酸化などの反応が鍵段階として 1,2-転位を含んでいるので、それらの共通点を探ろうと思います。
ピナコール転位
今回取り上げる1, 2-転位の共通点はズバリ次の3点です。
- 安定な分子の脱離が電子を引き出し、
- 隣接する電子豊富な原子が電子を押して、
- アルキル基が隣の原子に滑り込むように転位する。
これについて、ピナコール転位を例に挙げて説明します。

この反応機構の巻矢印は次のことを語っています。まず、出発物である1,2-ジオールの一方のヒドロキシ基がプロトン化されることで、そのヒドロキシ基は水という脱離しやすい置換基に変換されます。そして、水が脱離することでカルボカチオンを生じますが、ここでアルキル基の転位が起こると、新しいカルボカチオンは酸素のローンペアによって安定化されます。最後に酸素のプロトンが外れて、生成物のケトンを生じます。
引き出して押し出す
さて、上に示した一見すると長ったらしい反応機構を見やすくするために、一連の電子の流れの重要なポイントを、次のように無理やり1つの図にまとめて表してみます。

この図は「水の脱離がアルキル基を引き出しつつ、OH 基のローンペアがアルキル基を押し出す」と読みます。もっと手短に言うと、「引き出して、押し出す」です。このように表すと、多段階でややこしそうな反応機構の全体像を把握しやすいと思います。
というわけで、この指針に従って、1,2-転位を鍵段階に含む種々の反応を以下の表にまとめました。鍵段階の図を見れば、それらの個々の反応の類似性を見ることができると思います。
| 反応名 | 引き出し | 押し出し | 鍵段階 |
| ピナコール転位 | H2O の脱離 | OH 基のローンペア |  |
 |
|||
| Baeyer-Villiger 酸化 | R3COO– の脱離 | OH 基のローンペア |  |
 |
|||
| Tiffeneau-Demjanov 転位 | N2 の脱離 | OH 基のローンペア |  |
 |
|||
| Beckmann 転位 | H2O の脱離 | N のローンペア |  |
 |
|||
| ベンジル酸転位 | カルボニル基 | O– のローンペア |  |
 |
|||
関連反応
- ワーグナー⋅メーヤワイン転位 Wagner-Meerwein Rearrangement
- デミヤノフ転位 Demianov Rearrangement
- ウォルフ転位 Wolff Rearrangement
- アーント⋅アインシュタート合成 Arndt-Einstert Synthesis
- クルチウス転位 Curius Rearrangement
- ロッセン転位 Lossen Rearrangement
- ホフマン転位 Hofmann Rearrangement
- ボイヤー⋅シュミット⋅オーブ転位 Boyer-Schmidt-Aube Rearrangement
本連載の過去記事はこちら
- 第一回 有機反応を俯瞰する ーシグマトロピー転位
- 第二回 有機反応を俯瞰する ー[1,2] 転位 (本記事)
- 第三回 有機反応を俯瞰する ー付加脱離
- 第四回 有機反応を俯瞰する ー芳香族求電子置換反応 その 1
- 第五回 有機反応を俯瞰する ー芳香族求電子置換反応 その 2
- 有機反応を俯瞰するシリーズーまとめ