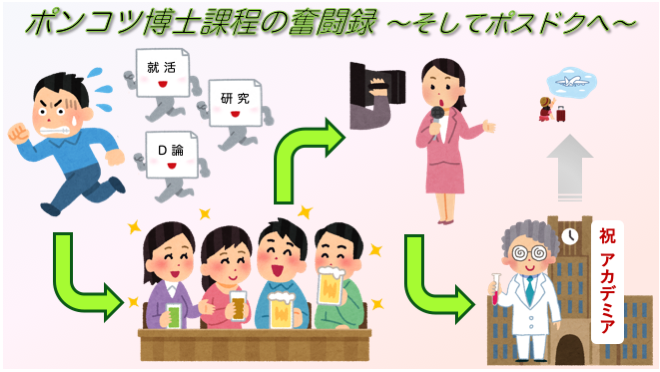「おーいあの仕事進んでるのかい? A君の方はだいぶ進んでるみたいだぞー」
人なつっこそうな笑顔がとても印象的で、こんな若輩の仕事のことも気にしてくださるフランクな先生。それが名古屋大学生命農学研究科坂神洋次先生に対する筆者の印象です。(写真はGCOEのページより引用改編)老若男女を問わず、酒席を共にし先生の薫陶を受けた若い研究者、研究者の卵たちは数知れないはずです。
農学畑の有機化学者で坂神先生の事を知らない者はありません。先生が微生物や植物から次々と見いだしてくる、極めて重要な生理活性天然有機化合物は、生物学者、化学者に強烈なインパクトを与えるものばかりでした。
しかし、我が国を代表する天然物化学の巨星とも言える坂神洋次先生は、膵臓ガンとの闘病も虚しく2012年4月9日にこの世を去ることになりました。享年63。まだ現役の教授職にありながらの突然の死は、先生のお人柄を知る私たちにはとても信じ難いものでした。
筆者は坂神先生に直接教えを請うたことがある訳でもありませんので、この追悼企画を執筆する資格があるのかは少し疑問なところです。しかし、少ないながらも一緒に仕事をさせていただき、筆者の研究者としての人生を変えるような大きなご恩を受けた身といたしまして、僭越ながら先生のご業績について甚だ簡単ではございますが紹介させて頂きたく存じます。尚、筆者の知る範囲で書く都合上、記事内容に誤りやご不快な点がある可能性がございますので、その際はご指摘いただければ幸いです。
坂神先生は、東京都立新宿高校を経て1972年に東京大学農学部農芸化学科を卒業、1974年には東京大学大学院農学研究科農芸化学専攻修士課程を修了されています。学生時代には生物有機化学を田村三郎先生、鈴木昭憲先生の元で学ばれました。
植物そして微生物ー東京大学時代ー
先生が学生時代に単離された記念すべき第一番目の化合物は栃木県西那須野で採集したアルファルファの根から単離したmedicarpin-β-D-glucosideです[1]。しかしながらこの化合物は含有量も比較的多い化合物であり(12 Kgから1.5 gの結晶を得ています)、アグリコンのmedicarpinはファイトアレキシンとして知られているのに対し、特に何か活性があるという報告ではありませんでした。

Medicarpin-β-D-glucosideの構造
その後1976年には博士課程を中退し東京大学農学部の助手になられています。当時は博士号を取得せずに助手となるのはそんなに珍しいことではありませんでした。
博士課程から助手の時代に手掛けた仕事にTremella mesenterica(和名コガネニカワタケ)の性接合物質があります。コガネニカワタケはその名の通り黄色いニカワのような形状をしたキノコです。しかし本菌の有性世代は酵母に似ていて、A型とa型と呼ばれる二つの接合型があり、互いに接合管を出し合って接合(受精のようなものと考えて下さい)することが知られていました。その接合管を誘導する物質の存在が示唆されていたため、坂神先生らはその単離に挑みました。培地100 Lで培養を行い、分画精製して得られたのはたった1.0 mgではありましたがtremerogen A-10と名付けられた活性化合物を得る事に成功しました。またその逆のa型が放出してA型に接合管を誘導する物質としてtremerogen a-13も得ております[2]。Tremerogenはシステイン残基がファルネシル基で修飾を受けているというユニークなペプチドでした。

Tremenogen A-10 (上)、tremenogen a-13 (下)の構造
この仕事により坂神先生は1979年には農学博士を取得すると共に1980年には農芸化学奨励賞をご受賞されております。
この二つの仕事はその後の先生の研究の方向性をよく表すものとなっています。即ち、ターゲットは主として植物もしくは微生物、そして特にtremerogen A-10のようにその生物に起こるなんらかの生命現象の“鍵”となる化合物の探索研究を生涯を通じて行っていくことになります。
1987年まで東京大学にて助手を努められ、その間1983年から1985年までは米国のThe W. Alton Jones Cell Science Center にてForeign Researcherとして動物細胞のグロースファクターについて研究されました。筆者の伺ったところによると米国では随分と激しく議論を戦わせ、互いに切磋琢磨されたようです。
内在性物質を追い続けてー名古屋大学時代ー
帰国後まもなくして1987年名古屋大学農学部に助教授として赴任され、1994年には教授にご昇任されました。
名古屋大学での研究では、切れのあるユニークでかつ重要な化合物を次々に単離構造決定していきました。ただ単に単離して構造決定するだけではなく、tremerogen A-10のときもそうでしたが、天然物の構造を修飾し、活性がどう変化するのか、いわゆる構造活性相関に関する研究や、ひいては活性発現のメカニズムを明らかにしていくなど、ある不思議な生命現象の観察から生まれる天然物化学の入り口から出口までを網羅する研究を展開されました。
特に筆者が印象に残っている化合物としては、トリプトファンが特異な翻訳後修飾を受けている枯草菌(Bacillus subtilis)のクオラムセンシングフェロモンであるComXフェロモンがまず挙げられます[3]。この報告はNature Chemical Biology誌の創刊号に掲載されておりその意味でも大変印象深いです。ケミカルバイオロジーなる言葉が流行する前から、坂神先生のやってこられた研究は正にケミカルバイオロジーそのものであり、時代が追いついてきたということでしょうか。

ComXRO-E-2フェロモンの構造
次に挙げるとすれば植物細胞増殖因子ファイトスルフォカイン(PSK)を忘れることは出来ません。先生は1980年頃以下の表を眺め、高等植物だけにペプチド性の信号物質が存在しないのは不自然であり、必ずあるはずだと常々考えておられたそうです。
ファイトスルフォカインの構造

表は文献[4]より引用(1980年頃は高等植物、ペプチドの欄は空欄であった)
また日本農芸化学会誌の総説に以下のような記述が見られます[4]。
筆者は、1974年頃に当時フランスから帰ったばかりの原田宏先生(当時東京教育大学農学部)から、通常の植物はホモジェナイザーで磨砕すると細胞がつぶれてしまうが、アスパラガスは細胞壁のついたきれいな単細胞が得られるということ、さらにこのときに得られる上清液を培養液に加えるとアスパラガス細胞の分裂が促進され、上清液には未知の細胞分裂促進物質が含まれる可能性が高いということを教えていただいた。筆者はこの実験を再現することができなかったが、磨砕によって得られたアスパラガスの細胞は顕微鏡下で非常に美しく印象的で、いつかこの系を使って研究をしてみたいと思っていた。
(文中斜体は筆者)
そして20年の時を超えアスパラガスの細胞を利用した巧みなアッセイ系を構築後、遂に1996年に高等植物のペプチド性の因子PSKの単離に成功し、PNAS誌に報告しました[5]。顕微鏡に映る美しい細胞、そしてそこから生まれたPSKという輝くような物質。これは偶然ではありません。この仕事は先生の研究に対する姿勢をよく表していると筆者は思います。そこに面白い化合物があるはずだという強い信念を持ち続け、そしてそのものを明らかにするのだというものとり屋の執念のようなものを感じるのです。またその後この研究を発展させ、PSKの受容体の同定にも成功しています[6]。坂神先生はこれら一連のPSKの研究により2003年日本農芸化学会賞をご受賞されております。
天然物化学と歩む道
ここで紹介しきれないのが誠に残念でありますが、坂神先生の200編にも及ぶ論文には、数々のユニークな化合物を中心とした化学と生物が含まれています。生理活性天然有機化合物の単離の研究はJournal of Natural Productsのような専門誌があるくらい溢れるように報告されてきました。しかし、近年では新しい生理活性や、新規の骨格を持った化合物はなかなか見つからなくなり、ともすれば天然物化学は終わったと揶揄されることもしばしばです。
しかし、抗がん剤や抗生物質のような医薬のシーズ探索だけがものとり屋の仕事だとは思いません。坂神先生の見いだされた化合物群は、ペプチドも多く含まれていることから、筆者のような有機合成化学者には一見単純で面白味のない化合物に映るかもしれません。しかし、得られた化合物の構造が単純であったとしても未解明の生命現象に挑み続け、そしてその構造を明らかにして初めて生まれる科学があるはずです。坂神先生の報告にScience誌、PNAS誌やNature Chemical Biology誌など、いわゆるIF値が高い雑誌が数多く含まれていることは、多くの科学者がその化合物の重要性を認めているということを表しています。
坂神先生の示してきた道は天然物化学の王道であり、そしてその道はまだまだ明るい未来へと続いているように思えるのです。
“天然生理活性物質、特に微生物・植物の内在性物質を明らかにし、作用機構まで解明すること” [4]
道半ばにしてこの世を去られた信念の“ものとり屋”坂神洋次先生のご冥福をお祈りいたします。

2008.9.10. 22nd Naito Conference on Chemical Biology [I]にて
関連文献
- Sakagami, Y.; Kumai, S.; Suzuki, A. Agric. Biol. Chem. 1974, 38, 1031. DOI: 10.1271/bbb1961.38.1031
- (a) Sakagami, Y.; Isogai, A.; Suzuki, A.; Tamura, S.; Kitada, C.; Fujino, M. Agric. Biol. Chem. 1979,43, 2643. DOI: 10.1271/bbb1961.43.2643. (b) Sakagami, Y.; Yoshida, M.; Isogai, A.; Suzuki, A. Science 1981, 212, 1525. DOI: 10.1126/science.212.4502.1525
- Okada, M.; Sato, I.; Cho, S.-J.; Iwata, H.; Nishio, T.; Dubnau, D.; Sakagami, Y. Nat. Chem. Biol. 2005, 1, 23. DOI: 10.1038/nchembio709
- 坂神洋次 日本農芸化学会誌, 2004, 78, 100.
- Matsubayashi, Y.; Sakagami, Y. Proc. Natl. Acad. Sci. 1996, 93, 7623. DOI: 10.1073/pnas.93.15.7623
- Matsubayashi, Y.; Ogawa, M.; Morita, A.; Sakagami, Y. Science 2002, 296, 1470. DOI: 10.1126/science.1069607