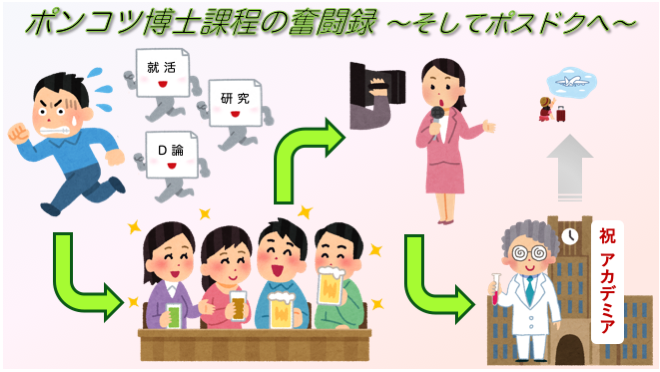今に始まったことではありませんが、理科離れ、あるいは科学離れという言葉をよく耳にします。それは小学生・中学生といった子供たちが科学に興味を持たなくなっているという話。
ところが最近では、「科学者の科学離れ」が進んでいるというのです。
これはいったいどういうこと?
科学者の科学離れと言われると不思議な感じがしますが……まずは簡単なチェックテストに協力してもらいましょう。
?Q1 自分のやっている研究についてある程度説明できる。
?Q2 自分の隣、あるいは前後の席で研究している人の研究についてある程度説明できる。
?Q3 自分と同じ部屋で研究している人の研究についてある程度説明できる。
?Q4 自分と同じ大学・会社で研究している人の研究についてある程度説明できる。
?Q5 日本の研究者の研究についてある程度説明できる。
?Q6 世界の研究者の研究についてある程度説明できる。
下の方のクエスチョンに関しては面倒臭くなってきたのでかなり漠然としていて、同じ分野の人の研究だけならわかるよ、とか、友人の研究なら説明できるぞ、とかいろいろあるかもしれませんが、まぁとりあえずはどちらでも構いません。
チェックしてみて気付くのは意外と周りのことはよく知らないということです。これって科学離れではないですか?
知らないということと興味がないということは別物なので、上述のチェックが少なかったからと言って一概に科学離れとは言えないかもしれません。しかし、同じ研究室の人の研究を知らないなどというレベルになってくると、勉強不足というよりは単に関心がない、すなわち科学離れの第一歩を進んでいるといっても差し支えないでしょう。
まぁこれを科学離れと呼ぶか否かは読者の判断にお任せいたしますが、いずれにせよ自分の研究に近い内容に関しては正確な知識を持っていたいですし、できる限り遠い分野についてもある程度のことは知っておきたいですよね。
しかし、研究者は周りに関心を持つにはあまりに自分すべき作業が多すぎますし、一口に同じ分野・他の分野といっても、幸か不幸か現代の科学研究のフィールドはあまりに広大で、簡単に勉強するのはとても難しいと思います。(何かいい勉強方法があるならば教えて頂きたいものですが)私の思うところを以下に綴ってみたいと思います。
人とよく話をする
上述の「同じ研究室の人の研究を知らない」などというのは、人と話をしていればありえないはずです。研究室によっては「私語禁止!」なんていうのもあるようですが、私は周りの人と研究の話をするのはとても良いことだと思います。
また、学会の懇親会に参加するのは意味あることだと思います。身内で固まっていたり、ただ飲食を楽しんでいるだけではあまり意味ないですが……
人に聞かなくても自分で勉強すればわかるワイ!と思っているそこのあなた。教科書や論文に書いてあることが、その研究の全てだとでも思っていませんか?
講演をよく聞く
当り前じゃないか、と言われるかもしれませんが……どんなに忙しい研究者でも、学会に来ているときには実験できません。それならよく聞いておいた方がいいでしょう。そして、できるだけ講演者に質問をするべきだと思います。質問をすると、案外その内容についていつまでも記憶しているものですよ。
日本語の雑誌を読む
英語の勉強にはなりませんが。化学の分野では、「化学」「現代化学」のような雑誌は重宝します。英語が得意な人でも、自分と違う分野の英語の雑誌はなかなか読めないことありませんか?「化学」「現代化学」は多様な分野の化学が詰まっていますし、かつ分かり易くまとまっていて私はとても好きです。
今回は、受け手側のあり方について個人的な意見を述べましたが、「科学離れ」しないためには発信する側も最大限に工夫する必要がありそうです。すなわち、いかに他人に分かり易く科学を説明するか、という部分にも努力しなければなりません。それには過去の記事を参考にしてみるのも良いかもしれません。